アンテナ技術と現場力でローカル5Gのユースケースを支える日本アンテナ
「日本アンテナは放送・通信の領域で幅広くアンテナを提供してきた。無線通信の分野では、自動車電話だった第1世代移動体通信システム(1G)から現在の5Gまで、一貫してアンテナを提供している」。こう語るのは、日本アンテナ 執行役員 経営戦略室担当の大嶋元樹氏だ。
日本アンテナは1953年に設立し、まもなく創業70周年を迎える。本社は東京・荒川区尾久に置き、全国23拠点と、埼玉県鴻巣市の川里工場と蕨市の蕨工場に生産施設と開発部隊を持つ。川里工場は都市部からは少し離れた立地だが、これには意味がある。大嶋氏は、「アンテナ技術の品質保証には、高周波的な評価が必要で、外部から電波的に遮断して無反射状態を保つ電波暗室が不可欠。こうした設備は都市部よりも郊外のほうが適した環境を用意しやすい」と説明する。川里には電波暗室が大小や周波数帯などの違いで4室、その他の試験設備なども完備する。
同社の事業領域としては、放送通信領域の製品販売、ソリューションがあり、これらが約8:2の構成比率でビジネスを成り立たせているという。今回のトピックは、無線通信領域、それも5Gおよびローカル5Gへの取り組みについて。またソリューションと関連深い領域ということになる。

1G、2Gから携帯電話の歴史とともに歩む
通信領域、それも移動体通信システムとの関わりの側面では、日本アンテナは日本の携帯電話市場の歩みにずっと寄り添ってきたといっても過言ではない。大嶋氏は、「携帯無線網との関わりは古く、過去はアナログ方式の自動車電話から始まった1G、デジタル化された2Gの時代から、通信事業者や携帯端末メーカーに通信用アンテナを提供してきた」とその歴史を語る。
2Gから国際規格の3Gへと移り変わるなかで、日本でも携帯電話は爆発的に利用が進んだ。「携帯電話のデザイン1つの違いでも、アンテナの特性が異なり性能の要求は厳しくなる。年に数回もあったモデルチェンジごとに、機種ごとの要求に応えられるように設計をし、コストでも調整し、奮闘していた。最盛期は月産数百万本にも上り、国内の携帯電話アンテナの供給シェアで8割に達することもあった」(大嶋氏)。引き出し式のリトラクタブルアンテナが付いていた時代の携帯電話を活用していたならば、かなりの人が日本アンテナ製品のユーザーだったのだ。
端末側だけでなく、基地局側のアンテナも供給している。ビルの屋上などに鉄塔に据え付けられている基地局のアンテナにも、日本アンテナの製品が使われていて、こちらでもユーザーとして関わりがある人が多くいるというわけだ。「4G世代のLTE、LTE-Advancedなどに向けては、多周波共用アンテナを開発、提供している。1つの基地局の設置には多額のコストがかかる。1つの基地局で複数の周波数に対応できるアンテナは、通信事業者にとってコストメリットがある。4G基地局の多周波共用アンテナは、20万本規模で運用されている」(大嶋氏)と語る。
モバイル用途に限らないバリエーションもある。現在で言うIoTの前身となったM2M(マシンツーマシン)通信が始まった2000年前後から、機器に設置するアンテナの開発、提供を始めている。自動販売機などを無線通信で結んで在庫管理を容易にするような用途で、日本アンテナの技術が用いられてきた。営業部第一営業グループスペシャリストの岸本知久氏は、「M2M用途で、さまざまな機器にアンテナをつける必要が高まった。大型電波暗室に自動販売機や自動車などの大きな機器を持ち込んで、アンテナ単体だけでなく機器と合わせて性能を出すサービスを提供してきた」と説明する。
一方で、地方公共団体などの自営無線通信網の構築にも力を注いできた。基地局の構成や顧客ごとのエリア設計などは、モバイル系の通信事業者向けに培った技術が生かされる。日本アンテナの強みとして大嶋氏は、「不感地帯、エリア改善など、エンドユーザーが必要としている電波の照射エリアを改善して、通信領域を確保する上で多様なビームを形成する技術的な提案をおこなってきた。また電波利用において、通信事業者に向けては、回線設計に確実に準拠した形で、高周波特性、機構的な特性を提供できることも強み」と語る。
ローカル5Gにつながる学び
M2Mや現在のIoTにつながるアンテナを広く提供していく中で、学んだこともある。通信事業者の基地局や携帯電話のアンテナとしての利用とは状況が異なるからだ。「M2Mなどの用途では、設置環境やユースケースを把握していないと、トラブルになることがある。日本アンテナの視点で、現場の利用において品質を担保できるように、環境やユースケースに適したアンテナを選んで提案することが必要だと学んだ。アンテナ選定の前段階からのサポート体制が、品質のポイントになる」(岸本氏)。
また、4Gの世代になるとグローバル化の波が国内にも押し寄せてきた。その1つの影響はアンテナの広帯域化だ。海外から700Mから2690Mまで対応している通信モジュールが流れ込んできた上に、通信事業者もグローバル展開を進めていたためアンテナも広帯域化への対応が必要になった。

さらにM2M、IoTも普及が進み、搭載機器が増えるようになった。するとアンテナの省スペース化が課題になる。携帯電話やスマートフォンでは外に伸びるロッドアンテナから内蔵アンテナへシフトしたように、M2Mでも内蔵アンテナへの要望が高まってきた。「4Gでは基地局と端末の間で複数のアンテナを使うMIMO技術が採用され、デバイスには2つのアンテナが入らなければならない。さらに複数の通信方式を選択して通信するコグニティブ無線では、1つのデバイスにアンテナを5つ格納することもある。アンテナの小型化だけでなく、干渉やアンテナの配置など、デバイスの開発前から関わりを持って最適なアンテナを提案する必要性がさらに高まってきた」(岸本氏)。
4Gまでで現れたトレンドは、5Gでも継続するだろうと岸本氏は説明する。「5Gになると高周波帯域を使うため、電波が届きにくくなる。設置環境や、アンテナを機器に内蔵したときに、減衰が大きく見られる。こうしたときに、日本アンテナがこれまで経験してきたような開発前からのサポートのノウハウが生きてくる」。
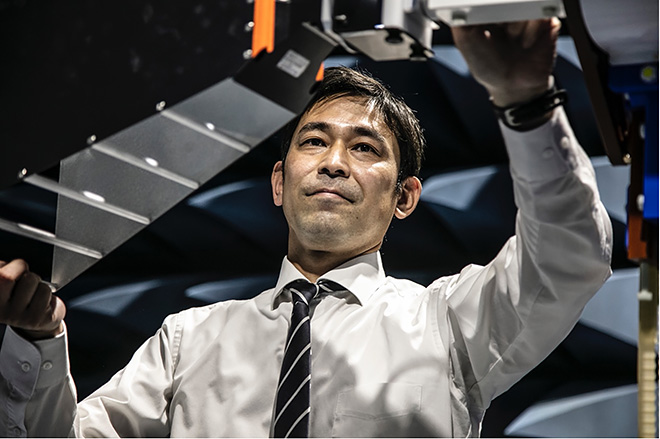
その上で、新しい課題として、環境や景観に配慮したアンテナの要望も高まってきている。「素材との融合、機器との融合などが、新しい取り組みになる。アンテナを多様な樹脂、フィルム、紙等に印刷する、ガラスにパターンニングするなどの素材にアンテナをマッチングさせる技術が進んでくるだろう。アンテナメーカーだけで完結できるとは限らないので、パートナーとしての素材メーカーや、通信事業者、地方自治体などと協業しながらものを作り上げていくことになる」と岸本氏は説明する。さらに、リサイクルできるアンテナなど、サスティナブル対応も求められると見る。
ローカル5Gへのニーズが見え始めてきた
世代を追って移動体通信をアンテナで支えてきた日本アンテナは、ローカル5Gへの取り組みも進めている。営業部第一営業グループ マネージャーの藤崎賢哉氏は、現状のローカル5Gに対応したアンテナのビジネスについて、「多くの企業や自治体からローカル5G向けのアンテナの引き合いがある。指定のエリアに収めるアンテナの指向特性は、30度以下、20度などの狭ビームの機能が要求される。ローカル5Gでは自社土地内だけにビームを飛ばし、他社土地に電波が出ないことが要件になるためだ」と語る。

そうした特徴はあるが、現在までの多くの引き合いのユースケースは、都市部近郊よりもパブリック5Gの電波が届かないような場所での利用が多いという。「海沿いにあるプラントなどで自営網を作りたいようなケースで、当てはまるのがローカル5Gという話が上がる。また北海道など他社土地への干渉の考慮が少なくて済むような地域で案件が進む傾向にある」と地域での適用の温度差を説明する。さらに、「1.9GHz帯のsXGP(自営通信用TD-LTE規格)でまずプライベートLTEを導入して、次のローカル5Gへのステップを考えるという段階にある」と現状を分析する。
ローカル5Gのユースケースとして、経営戦略室 R&Dセンター シニアマネージャーの瀧澤豊吉氏は防災、減災に注目しているという。「日本アンテナは、2017年から国土交通省の革新的河川管理プロジェクトに参画していて、クラウド型危機管理型水位計を北陸の4河川に納入し2019年から運用を開始している。920MHzの無線を使ったシステムで、水位や温度などの情報を収集しているが、今後映像のアップロードなどのニーズが出てきたときはローカル5Gがうまく適用できるだろう」(瀧澤氏)。河川の管理については、山岳地帯などに限らず、都市部でも内水氾濫による浸水などが起こり、情報収集の必要性は高まっていることもある。
そうした中で、「放送系と通信系の販売チャネルを持っている」(瀧澤氏)ことが、日本アンテナのソリューションの広がりにつながりそうだ。藤崎氏は「ローカル5GのアンテナをCATV事業者に納めていて、防災減災、地域の安心安全見守りサービスなどの実験を行っている。ローカル5Gのコストは加入者の割り算になるため、CATV事業者の場合には費用対効果が取れる可能性がある。静止画像しか送れない920Hz帯の通信に比べて、動画をリアルタイムで流せるローカル5Gならば、みるみる河川の水位が上がるような様子を見せることができ、避難の意識付けになるといった効果が得られる」と語る。

アンテナ技術で対応を進めるローカル5G
ローカル5Gのニーズに対して、日本アンテナはアンテナ技術を用いてどのようなソリューションを提供していくのだろうか。大嶋氏はこう語る。
「5Gやローカル5Gで高い周波数を扱うと、多くの基地局を設置する必要がある。世の中の既存の構造物を利用してアンテナを設置することが求められる。さらに、5G/ローカル5Gのアンテナは熱効率が低くなるため、マテリアルを生かしてヒートシンクと一体化したアンテナを作ることも考えている」。

アンテナの設置場所へのソリューションとしては、すでにソフトバンク、三協立山と協業して、街中にあるLEDで光る立て看板に5G基地局用アンテナを内蔵した“見えない”看板アンテナを共同開発した。街中の看板を5G基地局用アンテナにできれば、アンテナの設置場所の課題が解決できるというアイデアだ。マテリアルでも専業のメーカーとの協業を進める。日本アンテナが持つアンテナの知見と、他社の知見を合せることで、新たなソリューションを提供していく方向性である。

日本アンテナ自身のノウハウや蓄積した技術を生かす部分も大きい。例えば、ローカル5Gの課題になる他社土地への干渉の問題。「自社の照射エリアだけは平滑なレベルで照射しながら、隣には出さない技術が必要だ。そうした白黒はっきりつけたエリア設計に、培ってきたビームフォーミング技術で貢献できる。さらに今後、ユーザーの要望に応じた精緻なビームフォーミングをデジタル信号制御で行うための研究開発も進めている」(大嶋氏)。実際の現場でどのようにアンテナが使われてきているかを知り尽くしている日本アンテナだからこそ、部品としてのアンテナを提供するだけでなく、どのようにエリアを作って運用していくかまで含めたソリューションを提供できる。
今後の5Gやローカル5G時代に向けた方向性としては、M2M、IoTのさらなる推進への貢献を考えている。大嶋氏は、「単にデータを扱うだけでなく、データの持つ統計的な意味の利活用を考えていきたい。人間が介在できないような危険地帯はもちろん、工場などでも生産性向上が求められている。アンテナを介してやり取りするデータの利活用についても統計学やAI(人工知能)を適用して、統計的な利用から社会課題の解決に貢献したい」と語る。5G/ローカル5Gのユースケースが広がっていくこれからの世界を、日本アンテナの技術とソリューションが支えていくことになりそうだ。

